
村上龍の近未来・金融政治長編小説。
過去に何度も読んだが、久し振りに再読してみて驚いた。この小説が書かれたのは1984〜1986年、つまりバブル経済絶頂期よりもさらに前のことなのだが、2009年の金融危機の最中に読むと、村上龍が描いた近未来の世界のそれなりの部分が2009年には現実のものとなって日本を覆っており、改めて村上龍の先見の明というか知的想像力の鋭さには驚かされた。
世界規模の企業が政府を越える力を持ち、経済がグローバル化する中で日本は力を失いつつあり、保守政権は崩壊寸前で、アメリカ資本の外資系企業は日本人を単なる下級労働力と技術力の供給源としてしか見ていないなど、いやいやどうして1984年にここまで想像できただろう、と驚かされる。
長い物語はまだまだこれからが佳境に入っていくところなのだが、この物語のように、日本を救うために彗星のごとく現れたファシストがいない分、我々が住む現実の世界の方が、より希望がなく、尻すぼみになってしまっているような気がしてきて、なかなか憂鬱ではある。「ファシスト」という言葉はヒットラーやムッソリーニを思い出させるが、とにもかくにも愛国者なのである。今の日本に一番足りないものは、愛国的政治家ではないかと憂いでしまう。
いずれにしても、2009年に改めて再読する価値のある、力のある小説だ。村上龍にしてはSMとか変態性欲とかが殆ど出てこないのも良い。

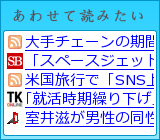

コメントする