
1954年に芥川賞を受賞した「アメリカン・スクール」を含む8編の短編を収録した小島信夫の初期短編集。
先日レビューを書いた庄野潤三の「プールサイド小景」との同時受賞であり、僕は庄野潤三と同様、小島信夫という作家のことをまったく知らなかったのだが、村上龍と村上春樹の対談集、「ウォーク・ドント・ラン」の中で二人が小島信夫の「アメリカン・スクール」を「良い」と賞賛していたため、どれどれということで手に取ってみた。
第二次大戦中の陸軍が舞台の話が多く、それが皆神経症的かつ細密描写的である。どれも短編なので、舞台やキャラクターの設定があえて詳細にはされておらず、それが逆に物語を「悪夢」のようなトーンに落とし込んで行く。ある意味芥川龍之介の短編のような、濃密な世界が広がっていく。
どの物語をとっても、共通して流れているテーマは、アイデンティティの喪失と恥という概念である。舞台が第二次大戦中のものも、終戦直後が舞台のものであっても、そこに描かれているのは、敗戦に伴い日本国民が強いられた大きなパラダイム・シフトであり、旧体制への羞恥である。
タイトル・クレジットの「アメリカン・スクール」では、終戦後に、日本人の教師達が地元に開設されたアメリカン・スクールを見学に行くのだが、そこにも「戦勝国アメリカ」に乗り込んで行く「敗戦国日本」の教師という構図がハッキリと描かれ、登場人物達は自分達の服装のみすぼらしさを恥じつつ、アメリカ軍兵士達がひっきりなしにジープで行き来する舗装道路を6キロに渡りトボトボと歩いていく。
じっとりと湿った湿度が貼り付くような世界観は、楽しくスッキリと読む世界観ではないことは確かだ。だが、この世界観こそが、日本が第二次世界大戦後に通過してきた、圧倒的な現実の世界なのだと思うと、不思議と頷けてしまう。
戦争で敵国民を殺して帰国し生き残った日本人の背負った闇とはこのようなものか。忘れ去られる時代なのかもしれないが、この時代の言葉は大切に残すべきだと感じた。
 |
|
||||||
|
powered by a4t.jp
|
|||||||


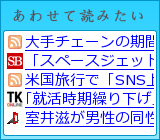

コメントする