
中上健次の初期短編集から2作目、「灰色のコカコーラ」。
一言で言ってしまえば、鎮静剤中毒の予備校生の無為な日々を綴った物語なのだが、全篇に漂う無力感と静寂感は何ともいえない緊張感をはらんでいる。
一人称で物語は進む。要はらりっている主人公が語り続けることになるので、鎮痛剤「ドローラン」が効いている時と効いていない時、効き方も激しい時とそうでもない時で、語り口が変化するし、途中で幻覚が現れて物語が中断したり、突然それまでと何の関係もない人物が現れて去って行ったりと、なかなかのリアリティーである。
本書の解説は村上龍が書いているのだが、村上龍は自身のデビュー作、「限りなく透明に近いブルー」は中上健次の本著、「灰色のコカコーラ」の影響を強く受けていると認めているとおり、ベースとなる世界観は共通のものがある。薬とジャズとモラトリアムである。
ただ、村上龍に比べ、中上健次がこの作品で描いた世界観の方が、より世俗的で安っぽいのだが、その分徹底的に足が地に着いていてリアルである分、迫力がある。村上龍の主人公はヘロインやメスカリンといった麻薬を常用していたが、本作の主人公はスーパーで安売りしている頭痛・生理痛の薬を大量摂取することで幻覚を見る。村上龍の物語では主人公は暴力を身近に感じるだけで自らが暴力を振るうことはしないが、本作で主人公は幻覚状態でアイスピックを用いスーパーマーケットの警備員を襲い、駐車中の車を破壊し、女学生を拉致し無免許で車を運転して事故を起こし、その女学生に怪我を負わせている。誰でも買える鎮痛剤でふらふらに酔った主人公は、何の感情の発露もなく、突如暴力的行動に出るのである。その理由なき暴力のリアリティーが、本作にはある。
物語のエンディングは非常に象徴的で、美しささえ漂っている。鎮痛剤ドローランを主人公は20錠まとめて飲む。それは彼にとっても新記録だった。「五錠は母のため、五錠は兄のため、姉のためにも三錠、アイスピックで刺された男のためにも三錠」(後略)。
そして20錠のドローランを飲んだ主人公は立て続けに水を飲みながら、さらに3錠の鎮痛剤を、拉致して怪我をさせた少女と、行きつけのジャズ喫茶店と、そしてマイルス・デビスのために飲もうと決める。


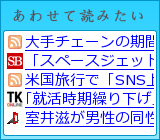

コメントする