
田中康夫のデビュー作、「なんとなく、クリスタル」。以前読んだ時はあまり感慨がなかったのだが、今回は色々と感じることがあり、面白く読めた。
本作が発表されたのは1981年で、執筆は前年の80年である。当時僕は小学校5年生か6年生で、この小説が話題になっているのはテレビで見て知ってはいたように思うが、この本を読むには幼すぎたし、マスコミが何を騒いでいるのかも理解していなかった。
だが、2009年に、39歳になってこの本を読むと、当時の自分を取り巻く環境や時代の雰囲気がまざまざと甦り懐かしい気持ちになった。当時の僕は港区西麻布在住であり、本書の主人公である由利と淳一が「共棲」する「コーポラス」がある神宮前からも近い、いわゆる「都心」に住んでいたことも要因の一つだろう。
今思えば、80年代前半は、その後訪れるバブルへと向かう、緩やかな繁栄の時期だったのではないかと思う。60年代の高度経済成長で貧困から一気に脱出し、その後70年代に襲いかかった石油ショックを乗り越えた東京人達は、次の好景気へと向かって生活水準を切り上げつつ、生活を謳歌していたように思う。
主人公の由利と恋人の淳一は二人とも大学生ではあるが、由利はファッションモデル、淳一はフュージョンバンドのキーボーディストとしての収入があり、親に依存せずに自活しているが、生活には余裕があり、都心に暮らしながらも生活を楽しみ、謳歌する余裕がある。彼らの生活は僕が大学生時代だった頃の大学生像とそれほど大きな違いはなく、いかにも「今どきの若者」という感じがする。
だが、この小説が書かれた1980年と2009年では、日本の若者を取り巻く環境は大きく変化してしまっている。その中でも最も大きな変化は、日本という国が持つポテンシャルの著しい低下と、将来に対する希望の消滅だろう。
物語の中で由利が自分の将来について想いを馳せる部分があるのだが、その姿は、自分の将来はきっと今より良くなる、という根拠のない期待と自信に溢れている。それは由利だけに限ったことではなく、80年代当時の東京には、そのような根拠のないふわふわとした期待や自信が、まるで春の宵みたいな優しい何かが、そこら中に漂っていたように思う。
そういった根拠のない自信や期待は、今の若者の顔からは見ることができない。それは、多くの国民が今感じている閉塞感を、社会的弱者である若年層世代が代表して受け入れているからに他ならない。今の大学生達は、由利達や僕達のように、「なんとなく気持ちいい」、「なんとなく楽しい」という風に生きているだろうか。いや、今の若者はもっと真剣に生きているように思う。
この「なんとなく、クリスタル」にはストーリーらしいストーリーもないし、始まりもなければ終わりもない。由利が一人称で語る切り取られた日々が淡々と綴られているだけである。そこには夥しい固有名詞が挿入されていて、その多くはファッションブランドの名前であり、当時流行していたミュージシャンやバンド名であり、また彼らが演奏する曲名であったりする。その固有名詞一つひとつに田中康夫は註を付けた。当時は「そんな解り切った物事にいちいち註を付けて奇をてらっている」という批判もあったようだが、時代を経て読むと、ブランドやミュージシャンの中には時間の洗礼を受けて消滅したものも多く、この膨大な注釈は正しく機能し始めているようにも感じられる。
80年に大学生だった由利が実在の人物ならば、2009年には50歳前後ということになる。50歳になった由利は、「なんとなく」生きているだろうか。「クリスタル」という言葉はあまりにも陳腐化してしまったが、この小説は1980年という時代を見事にパッケージ化し、瑞々しいままに保存してくれている。良い時代だった。そんな言葉が出てくるのは、僕が歳を取ったということだろうか。でも僕にはこの時代が懐かしいとともに、とても羨ましくもある。
 |
|
|||||||
|
powered by a4t.jp
|
||||||||



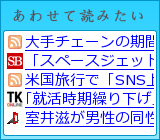

コメントする