
「パパは楽しい躁うつ病」は、芥川賞作家で歌人斎藤茂吉の次男であり、さらに精神科医でもある北杜夫氏と、その一人娘でサントリー株式会社に勤務しつつエッセイストとしても活躍している斉藤由香氏の二人が、父北杜夫が30年以上患ってきた躁うつ病について明るく楽しくあっけらかんと語る対談型エッセイ。
北杜夫といえば「どくとるマンボウ航海記」で、僕も小学生の頃にずいぶん彼の著作を読んだものだが、今回久し振りに著書を手に取って驚いたのだが、彼はもう81歳なのだそうだ。でも良く考えれば「どくとるマンボウ」が書かれたのは僕が生まれる前なのだから、作者が81歳になっていたとしても別に驚くことではないはずなのだが、なんだかビックリだ。
この親子対談は、原則時系列に沿いつつ、父北杜夫が躁うつ病を発症する前の平和な時代、そして病気の発症時期とその症状についての説明が明るくあっけらかんと進められていくのだが、「躁うつ」と言っても、圧倒的に「躁病」の時の記述が多く、「うつ」についての記載はほとんどない。
現代においては「うつ」は日本の国民病のような扱いを受けている感もあるほど広く認知され、その症状や対策などについても国民の間に一定の理解は広まりつつあるように思うが、「躁」については、「うつ」ほど広くその症状や対策は認知されていないのではないかと思うのだが、読んでいてまあ圧倒されるというか呆れるというか、「大躁病」状態の北杜夫の行状はまさに異常で、なるほどこれは病気だわいと納得させられる。
幾つか強烈な例を挙げると、大躁病状態になった北杜夫氏は「映画を作る」と叫んで突如株の信用取り引きを同時に4社の証券会社と始め、見事にすってんてんになり、ついには破産してしまう。さらには「マンボウマブゼ共和国」なる国を作り日本から独立を宣言し、独自の通貨やタバコを作成・発行し、「文華の日」には遠藤周作ら知人を呼んで「文華勲章」授与式を開催し、この授与式にはフォーカスやテレビなどのマスコミまでが押し掛けたという。
軽井沢の別荘滞在中、真夏の夜にすべての窓を全開にして家中の灯りを付け、吸い寄せられてきた大量の蛾をたたき落とし「昆虫採集」を強行したり、短波放送で株式市況を、ラジオで英会話と中国語会話を、さらにステレオでベートーベンを、同時に大音響で響かせるなど、まあ読んでいるだけでこちらが疲れてしまうような凄まじさだ。
救いは全篇を通じて娘の斉藤由香がとにかく明るく楽しく父の病気と触れ合ってきた様子がリアルに伝わってくる点だろう。彼女の「天然」とも思える明るさによって、父の病気とその症状に振り回される家族はどんなにか救われたであろうことが想像できるし、父も娘に感謝している様子が文章からも伺える。
そして北杜夫自身が自負している通り、彼が文筆家兼精神科医として、自らの躁うつ病を積極的に開示して生きてきたことは、日本における躁うつ病認知において大きな貢献であったのだろう。彼が躁うつ病を発症して間もない頃は、「うつなので原稿が書けない」と編集者に告げても、編集者は「うつ」の意味を理解しなかったそうだが、今や「うつ」を知らない日本人はいないぐらいに広く認知されてきた。
というわけで楽しく読みつつも圧倒されたり呆れたり同情したりとなかなか忙しい本なのだが、全篇を通じて娘斉藤由香の父北杜夫に対する愛情が、一見無神経そうな発言の合間合間に垣間見えてちょっとだけ切ない。父北杜夫はもう旅行に行く気力も外を散歩する体力もないほどに老いているそうで、このままではもう本を出すこともできないと感じ取った娘が父との対談という形で、彼のライフワークともいえる「躁うつ病」に関する本を、二人の連名で出版したというのは、娘から父への最高の贈り物なのではないだろうか。
なかなか感慨深い本であった。久し振りに「どくとるマンボウ」でも読んでみるかな。
 |
|
|||||||
|
powered by a4t.jp
|
||||||||



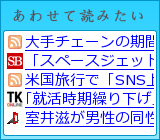

コメントする