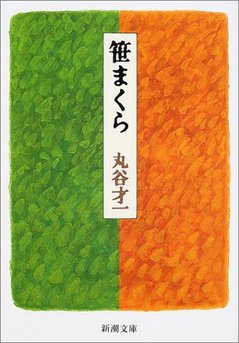
丸谷才一氏の「笹まくら」を読了。
色んな意味で凄い小説だった。もっと早く読むべきだったし、もっと早く丸谷才一氏の「小説」と巡り会うべきだった。
今回この「笹まくら」を読むことになったのは、ちびりちびりと楽しみつつ読み続けている米原万里氏の「打ちのめされるようなすごい本」の中で、米原氏が「打ちのめされるようなすごい小説」と題してこの「笹まくら」を激賞していたからなのだが、実はそれまで僕は小説家としての丸谷才一氏には、ほとんど興味を持っていなかった。
わざわざ『小説家としての』と断りを入れたのには意味がある。僕にとって丸谷才一氏というのは、僕の青春の書の一つ、ジェイムズ・ジョイスの「ユリシーズ」の翻訳者であり、それ以上でも、それ以下でもなかったのである。
そして、「ユリシーズ」に強く惹かれ、人生で2度も翻訳を出版してしまうような人物がどんな小説を書くのかについての興味を一度も持たずに20年近く放置してきてしまったことを、この「笹まくら」を読了した今、深く恥じている次第である。本当に、もっと早く読んでおくべき小説だったし、もしこの小説を25歳までに読んでいたならば、僕自身が書いた小説も、もっと違った形のものになったかもしれない。
***
「笹まくら」の主人公は二つの名前を持ち、二人の女性と生活を共にし、そして二つの時代を生きている。物語は精密に構成され、登場人物の描き方は鋭く鮮やかで、そして舞台の設定とストーリーの展開はスリリングで激しい。
昭和40年と昭和15〜20年という二つの時代を物語は行ったり来たりする。主人公浜田庄吉はごく普通の大学職員として暮らしているが、彼には大きな秘密がある。それは、彼が第二次世界大戦中に、国による徴兵を逃れて逃亡した「徴兵忌避者」であり、その期間彼は杉浦健次という別名を持ち、砂絵師兼ラジオと時計の修理屋として、憲兵と警官から逃げるために全国を旅して暮らしていたという事実である。
現代の彼、浜田には一回り以上年齢が下の若く美しい妻陽子がいる。一方戦時中の彼、杉浦健次には年上の同棲者阿貴子がいた。医者の息子としてインテリ階級に育った浜田と場末に場を張り砂絵を描き身銭を稼ぐ香具師として底辺の生活をする杉浦。高度成長期の「現代」と破滅へと向かう大戦中の日本。物語は二つの時代と二つの名前を持つ主人公の間を緻密に行き来しつつ、高い緊張感を持って細密描写のように展開していく。
徴兵という最も厳重かつ過酷な国家の要求から見事に逃れ切り、自由を獲得したはずの浜田だが、現代における彼の生活には勢いがなく、職場は息苦しく、妻との生活にも喜びがあまり感じられない。一方で、逃亡者杉浦として生きた時代の彼は、名前や生い立ちを隠し、常に追い立てられて生きていたが、圧倒的に自由であった。
現代と戦時中、二つの時代はシームレスに連続し、複合的かつ立体的に展開する。章立てが変わることもなく、行間を空けることもなく、突如時代は25年前に遡ったり、急に現代に戻ったりする。戦時中の話は時系列に沿っておらず、遡ったり戻ったり、場所もあちこちに移っていく。僕ら読者は最初この唐突な時代と場面の変更に戸惑うことになるが、この技法が「笹まくら」を圧倒的な作品へと昇華させる一つの大きな特徴となっている。
もう一つ強調しておくべきは、丸谷氏がジョイスが多用した"Stream of Consciousness"(意識の流れ)の技法を要所で使って来ていることで、これも見事に成功を収めている。登場人物が何かを考える際に、本筋とは関係のないことを合間に考えてしまったり、途中で考えていたことの題材が変化してしまったりする。そんな人間の思考の当たり前の流れを、そのまま言葉に載せてしまうという手法だが、この手法の挿入が、小説に彩りを添えるのに、際立った効果を現している。
物語は、昭和15年晩秋に、浜田庄吉が徴兵され入営を迎える前日に、壮行会の準備をしている実家から「床屋に行く」と行って出かけ、そのまま逃亡生活へと入る場面で終わっている。物語の最後は「終わり」ではなく「始まり」になっているのだが、このエンディングの持つパワーは凄まじく、思わず鳥肌が立ってしまう。
そして読後感には、村上春樹の「ノルウェイの森」や村上龍の「コインロッカー・ベイビーズ」に似た何かを感じた。何が共通しているのだろうとしばらく考え、それは物語が前にぐっと進むところで完結し、結末を読者に預けているという手法が共通しているという点に加え、その結末が、力強くそして挑戦的であり、未来に向けて大きな一歩を記そうとする瞬間にバッサリと物語が途切れる、というエンディングが、両村上作品と共通する強い読後感を与えてくれるのだと、思い至った。
名作。
 |
|
|||||
|
powered by a4t.jp
|
||||||



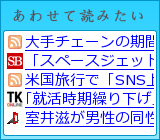

コメントする